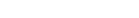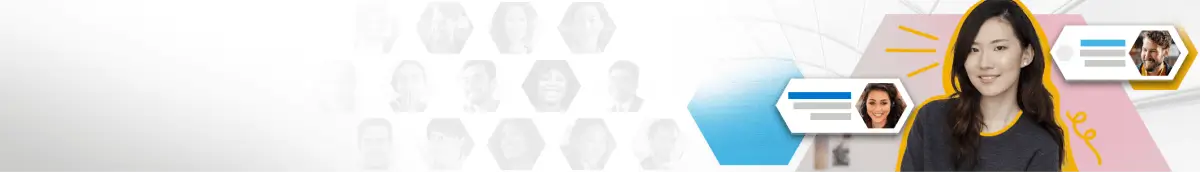未解決
35 メッセージ
1
505
ECS解説 第16回 ObjectScale V1.0のご紹介
皆様、こんにちは。
今回、今年2月に正式にリリースされましたObjectScaleをご紹介したいと思います。
本ブログは弊社デル・テクノロジーズのオブジェクトストレージ製品であるECS関連の情報をお届けしていますが、ここでObjectScaleを取り上げるのは、ObjectScaleがECSのコードを拡張し、純粋なソフトウェア・デファインド・ストレージ(SDS)のオブジェクトストレージとして製品化された、ソフトウェア製品がObjectScaleだからです。つまり、ObjectScaleはECSの兄弟製品となります。
ObjectScaleの概要
ObjectScaleとはどのようなソフトウェアでしょうか。コンテナアプリケーションとしてKubernetes環境で展開されるソフトウェア製品です。RedHat OpenshiftまたはVMware vSphere/Tanzu環境をサポートするソフトウェア製品としてリリースされました。すでにお客様がこれらのKubernetes環境をご利用であれば、ObjectScaleをコンテナアプリケーションとして既存のコンテナ環境にご導入いただけます。
ObjectScaleもECS同様、複数ノードで構成される分散型ストレージです。各分散ノードはKubernetesを介した複数のコンテナになり、ストレージサービスの展開も随意にKubernetesを使用して、他のアプリケーションのコンテナと同様に展開することができますが、データを保管するストレージですので、ハードウェア障害にも耐えうるよう、データを保存するディスクもしくはストレージ領域、ノードのハードウェアが相互に独立した領域に展開されます。下図のようにManagementのPodとデータを格納するStorageのPodを一つのノードに同居させることもできますが(推奨はノードを分けた構成です)、イレージャコーディングのフラグメントを保管する残りのStorage Podもそれぞれ異なるノードに展開することになります。
KubernetesのNetworkのポリシーを使用することができ、サーバー負荷分散装置も必要ですが、vSphere+Tanzu環境ではNSX-Tを用い、RedHat OpenShift環境ではビルトインのMetal LBをデフォルトでご利用いただけるようにしてあります。テナントとしては上記のマネジメント、複数のストレージのPodをまとめたObject Storeがテナントとなります。テナント間で物理ノードを共有することも占有することも可能です。
プラットフォームが十分にリソースを提供してくれるのであれば、お客様のアプリケーションとObject Storeを同居させることも可能です。
今後のリリースでCSIもサポートする予定です。CSIによって、Kubernetesがアプリケーションのコンテナ展開すると同時に、ObjectScaleのObject Storeをアプリケーション専用のストレージ領域として展開することを連動させることができるようなると期待されます。
コンテナ環境で稼働するアプリケーションからみると、パーシステントボリュームの管理はかなり難しいものですが、オブジェクトストレージであれば、書きだしたいとき、読み出したいときだけアクセスする疎結合のストレージとして、コンテナ側が接続状況を常に気にせずに利用が可能です。さらにオブジェクトストレージはデータアクセスの管理やリテンション機能など強力なデータセキュリティを実現でき、かつ耐障害性が高い一方でストレージ領域の拡張性が高く、レプリケーション等のデータ管理が容易なデータ保管に適切なストレージです。
ObjectScaleのようなコンテナベースのオブジェクトストレージであれば、アプリケーションを展開したいときに、はじめてコンテナ環境のリソースから必要なオブジェクトストレージ領域を切り出すことができ、コンピュートリソース、ディスクスペースの有効活用にも貢献することができます。
コミュニティエディション
ECSでは、GitHubから機能認の目的でお客様やパートナー様に無償でご利用いただけるコミュニティエディションをご提供しております。今回ご紹介するObjectScaleもコミュニティエディションをご用意しております。
公開先はECSと異なり弊社のサイトからになりますが、下記のリンクからアクセスいただけます。
https://www.dell.com/en-us/dt/software-downloads/index.htm
上図のアクセスいただいたサイトのメニューにある赤丸で囲った「UNSTRUCTURED DATA STORAGE」をクリックいただくと、下図に遷移します。
コミュニティエディションのご利用は無償となります。ダウンロード前にAgreement Pageにてご了解をいただいてからダウンロードいただくことになりますが、前提はトライアル、検証等の目的とするご使用になります。
以下のコミュニティエディションのご利用上の制約がありますので、ご注意ください。
- 最大容量は30TBまでになります。
- 単一インスタンスのみとなり、シングルテナントのみでの利用になります。このため、Replication機能はサポートしておりません。
- RedHat OpenShiftまたはVMware vSphere + Tanzuの環境へのご導入となります。
導入ガイドも、同サイトからダウンロード可能です。ご興味ありましたら是非トライしてみてください。
また、ユーザーインターフェースや機能を簡単に確認するうえでは、パートナー様にもご利用いただける弊社のDemo Centerからもご確認いただけるメニューが準備されています。
ObjectScaleの管理ポータル(管理用ユーザーインターフェース)へログインすると次のようになります。
Object Storeを表示させると次のようになります(Demo Centerなので、一つだけしか存在しません)。
ObjectScaleの機能特長
ObjectScaleはECSと異なりS3専用です。S3aもサポートしていますので、最新のHadoopから直接ObjectScaleに読み書きしていただくことが可能です。S3専用に絞ったことで、今後のS3の拡張にも追従がしやすくなりました。
ECSになく、ObjectScaleに実装されたS3の機能として以下のものがあります。
- S3 Notification
指定したバケットにオブジェクト操作(追加、削除など)があった際に設定した通知を送信するようにできます。
- バケット間レプリケーション
バケット同士でオブジェクトをレプリケーションすることができ、最大1000バケットまでターゲットにすることができます。
- フェデレーション
ObjectScaleもマルチテナントをサポートしています。ECSはテナントをネームスペースで実現しました。これによってテナント間のユーザー認証連携ができない、論理的な分離をしっかりと行っていました。特定のユーザーではテナント間を跨いで利用したいというご要望もあり、ObjectScaleではテナント間でIAM認証を相互に連携できるようフェデレーションという関係を作ることができる機能をサポートしました。
ObjectScaleのライセンス
現在のリリースではサブスクリプションモデルで、12か月または36か月の期間でご利用いただけるサブスクリプションをご購入いただけるようになります。ライセンスの単位は、ストレージ容量になり、利用に必要な技術サポートも含めたライセンスになります。また、永続的にご購入を希望されるお客様には、企業のお客様とデル・テクノロジーズのソフトウェアライセンスを永続的・包括的にご購入いただくTLAライセンス契約でご購入いただいているTLAライセンスの一部をObjectScaleの容量ライセンスに割り当てていただくことで永続的ライセンスとしてご利用いただくことが可能になります。
1TBからご購入が可能ですが、ご購入容量が大きくなるほど容量単価は小さくなるようになっております。
ObjectScale利用環境の要件
概要でもご説明したようにObjectScaleの一つのObjectStoreを構成する複数のストレージPodが展開される物理的なノードはPodごとに独立した物理ノードが必要です。アプリケーション利用を想定していない、各物理ノードの最小推奨構成は下記のようになります。
補足となりますが、VMware Tanzuの場合、VSANが前提となります。この場合、VSAN DirectかVSAN SNA FTT(フォールトレラント)=0を指定して冗長化しない、つまりノード外にレプリケーションしないように設定してください。データの冗長化はObjectScaleのイレージャ・コーディングによってフラグメント化され、冗長化されたフラグメントともに、複数のPod(物理ノード)に分散され、データ保護されます。また、ネットワーク機能にはNSX-Tを利用します。
RedHat Openshiftの場合、必要な本数の物理ディスクを各ノードでストレージ用に占有させてください。
おわりに
ObjectScaleはリリース直後ということもあり、ご案内を始めたばかりですが、海外では大手のコンテナユーザーを中心に、ご導入を決定されたお客様がいらっしゃいます。コンテナイメージのレポジトリストレージとして利用するだけでなく、SSDを積極的に利用して、アプリケーションから高速アクセスを検討されるお客様もいらっしゃるとのことで、より広範囲なオブジェクトストレージのユースケースが増えるのではないかと期待しています。また、2022年のDell Technologies Worldで発表されたProject Alpineのソフトウェア・デファインドのオブジェクトストレージは、当然ObjectScaleを前提にしていると聞いています。今回は触りだけですが、新たなソフトウェア・デファインド・ストレージ製品としてKubernetes環境のオブジェクトストレージをご紹介いたしました。
これからも、ECSに加え、ObjectScaleのトピックもアップデートしてまいりたいと思います。ご興味のあるトピックがありましたら、ぜひお知らせください。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします。
杉本 直之
デルテクノロジーズ株式会社
UDS事業本部SE部
過去のブログ一覧
ECS解説第14回 ECSの改ざん防止(WORM)機能のまとめ
ECS解説第13回 新機能 S3 Object Lock のサポートについて(後編)
ECS解説第12回 新機能 S3 Object Lock のサポートについて(前編)
ECS解説第11回 Community Edition 最新版(v3.6.2.0)リリースのご案内
ECS解説第10回 ECS3.5の新しい機能(2) - オブジェクトタギング(Object Tagging)
ECS解説第9回 ECS3.5 Community Edition VM版
ECS解説第7回 s3curlにおけるECS3.5.0.2以降での操作方法の違いについて
ECS解説第6回 新しいオブジェクトストレージアプライアンス、オールフラッシュ版ECS EXF900追加のご紹介
ECS解説第5回 GeoDrive2.0のご紹介とウィンドウズシステム-ECS間のデータアーカイブ操作例 -Windows OS用オブジェクトストレージゲートウェイ・アプリケーション-
ECS解説第4回 s3curlによるECSの操作について(2/2)
ECS解説第3回 s3curlによるECSの操作について(1/2)
ECS解説第2回 ECS (Elastic Cloud Storage) TEST DRIVEのご紹介
ECS解説第1回 Elastic Cloud Storage (ECS) Community Edition (VM版) 最新版ご紹介