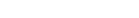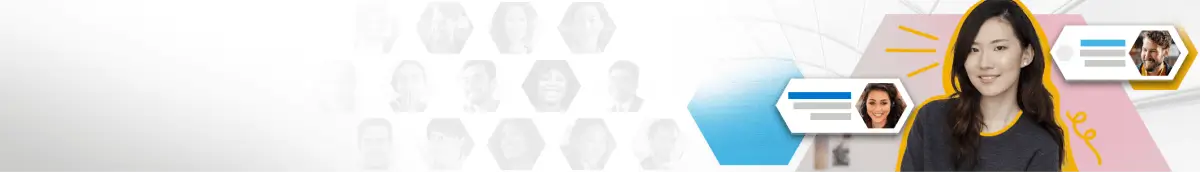未解決
19 メッセージ
0
186
[Coffee Break] 電車とpowerscale
おはようございます。Powerscale製品SEの貝原です。
本日は
電車の話です。
Powerscaleのプレゼンにおいて昔から伝統的に使われてきた手法、『電車で分かるスケールアウト』をご存知でしょうか? 電車とストレージには面白い共通点があります。それを使って一般的なスケールアップ型ストレージとPowerscaleの動きの違いを説明するプレゼン方法です。
今回は『電車で分かるスケールアウト』の簡単な内容説明と、電車に詳しいとついついやってしまう『よくあるツッコミ』を小話に添えて投稿します。
『電車で分かるスケールアウト』ですが、これはどういう話かと言うと、
強力なモーター(動力)を持つ機関車+それに引っ張られるモーター無し客室車両
➡一般的なスケールアップ型ストレージ
各車両が自走可能なモーターを持つ電車
➡スケールアウト型ストレージ(Powerscale!)
という例えです。
鉄道に詳しくないと何言ってるか分からないですよね。。。絵も合わせて見てみましょう。
一般的なスケールアップ型ストレージは、乗客が居る客車を、乗客が居ない機関車が引っ張るイメージです。乗客=データと考えて下さい
先頭が機関車であり、モーターが付いています。走行のパワーは先頭の機関車に全依存する為、機関車に余力があるうちは客車を増やせますが(ストレージ界ではディスクのみのスケールアウトに相当)、機関車のパワーが不足すれば機関車をよりパワーのあるものに交換(スケールアップ)するしかありません。
ちなみに現実の機関車+客車はこの様な感じです。
先頭の車両が機関車です。その後ろにモーターを持たない客車が付いています。写真はトワイライトエクスプレスと言い、大阪~札幌間を結ぶ豪華夜行列車として活躍していました。残念ながら今はもう走っていませんが、そのコンセプトはトワイライトエクスプレス瑞風という超々々々豪華列車に引き継がれています。(お1人様40万円~100万円とかします)
実はフランスが誇る高速特急TGVもこの「機関車+客車」の形式です。先頭車両には超強力モーターが詰まっており、人は乗れません。(TGVの場合は最後尾車両も機関車です)
対してPowerscaleのイメージは普通に良く見る電車です。全ての車両がモーターを持っていて、かつ人も載せることが出来る。人=データを増やしたければ、ただ車両を連結していけば良いだけです。
実際の電車はホームの長さ等で制限がかかっちゃいますが、Powerscaleにそんなものは関係ないので、252両まで連結することが出来ます。252両の客車を引ける様な機関車はそうそう無いでしょう。こうやってただひたすらにモーターを持つ車両を連結(スケールアウト)していく、それがPowerscaleのスタイルです。
電車は普通に馴染みがあると思いますが、あえて写真を載せれば
はい、山手線ですね。
ここで鉄道有識者様からよく入るツッコミがこれです。
「電車の先頭車両って、普通モーター付いてないですよね。だったら例えるのは新幹線の方が良いですね!」
と。
このツッコミがお客様から来たら、その後の宴は約束された様なものです。このあと5時間は熱く語り合えることでしょう。確かに大体の電車、特にJRの先頭車両の多くはモーターが付いていません。対して新幹線は先頭車両もモーター付きです。
伝説の新幹線500系。その近未来的なスタイルが最高に格好良かったですが、乗り心地が最悪と言われて流行らなかった残念な新幹線です。
逆に見てくれはいまいちだけど乗り心地が最高な700系はロングヒット。世の中の真理が垣間見えます。
ただまぁ、
この表現を突き詰めた場合、Powerscaleは全てのノードが同等であり、どのノード同士を組み合わせてもクラスタを形成出来る、という点も表わさないといけません。そもそも運転台(制御室)が付いていない車両はモーターがあっても単体では走れませんし、パンタグラフが付いていない車両も単体では電気の供給を受けられない=走れません。
全車両に運転台があり、モーターがあり、パンタグラフがある、そんな完璧なモデルを求めるなら、都電荒川線(現:東京さくらトラム)の様な路面電車が、沢山連結されている様な絵になることでしょう。正直あまりかっこ良くはないですね。
更に突っ込めば、各車両間で人(データ)が自由に行き来出来るのもPowerscaleの特徴ですし、路面電車の連結ではそれは表現出来ていません。普通の電車か新幹線くらいで手打ちにするのが良いでしょう。
あと先頭車両とは別に、殆どの車両でモーターが付いていないのが『グリーン車』です。
グリーン車は乗客の快適性を重視する為、音や振動がするモーターを積んでいません。逆にそのお陰で床下を乗客スペースに使えるので、東京近郊では2階建てが一般的です。
こういう話を面白いと思って頂けたのなら、今度電車に乗る前に、電車の側面に書かれた車体名を見てみて下さい。例えばここには、
モハE235-89
と書かれています。E235はシリーズ名みたいなものです。最新の山手線はE235系というシリーズです。-89は製造番号なので、これもあまり気にしなくて良いです。注目したいのはモハというカタカナ。これは車両の特徴を表しており、このルールはJR共通です。
ク:先頭車
モ:モーターを積んでいる
サ:モーターを積んでいない(先頭車では省略される)
ハ:一般車
ロ:グリーン車
となっています。
例)
クハ:モーターがない先頭車で一般車
クモハ:モーターがある先頭車で一般車
モハ:モーターがある中間車で一般車
サハ:モーターがない中間車で一般車
サロ:モーターがない中間車でグリーン車
モの文字がない車両はモーターが積まれていないので、他の車両に比べて静かです。狙って乗ってみると面白いかもしれませんが、探すのは大変ですね。ちなみに山手線の場合は1,4,7,10,11号車がモーターなし車両です。
ちなみこれは一般電車のルールであり、気動車(ディーゼルカー)、客車、機関車などはまた違うルールで命名されます。もしご興味があれば調べてみて下さい。またJR以外の私鉄はそれぞれが自由に命名するので、特に共通のルールはありません。
いかがでしたでしょうか?かなり電車(鉄道)寄りの話になってしまいましたが、こういう知識も持ってPowerscaleに接すると、より親近感が沸いて頂けるかも知れません。
最後までご覧頂きありがとうございました。